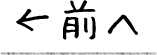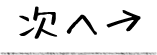高いジャグリング熱に浮かされています。
というのも、日本ジャグリング協会が主催する「ジャパンジャグリングフェスティバル」(通称 JJF)で行われるコンテスト「チャンピオンシップ」に先日審査員として参加し、尖ったジャグリングの数々に触れたばかりなのです。
レベルが高く、そして、個性的なジャグリングの数々に、興奮いまだ醒めやらず。おかげで稽古にも身が入ります。
10年後のジャグリングはどうなっているのか。
今から10年前には現在のような状況はとても想像できませんでしたが、ジャグリングの表現も多様化している現在を見渡すと、この先の10年後はさらに想像が難しい。
 世界を見据えるハードパンチャーしんのすけ
世界を見据えるハードパンチャーしんのすけそんな中でもひとつ言える「プロジャグラー」への流れがあります。
それはコンテストでの受賞をひとつのステップとしてプロジャグラーとして活動をはじめるケースが多い、ということです。前回の当コラムで紹介させていただいたSenjyuさんもそのようなステップを経ていました。
コンテストを目標とすることで、ジャグリングと向き合い、また同じ目標を持つジャグラーと切磋琢磨して行く。そのことが現在のジャグリングの頂きをぐいぐいと高いものにしていることは、今後も変わりないでしょう。
では、ジャグリングのコンテストにはどのようなものがあるでしょう。はじめに現在のジャグリング事情を「コンテスト」という視点からみてみましょう。
◆ジャパンジャグリングフェスティバルチャンピオンシップ
先にも触れた日本ジャグリング協会が主催するジャグリング大会で行われるコンテストです。2011年は男子個人/女子個人/チームの三部門がひらかれました。
チャンピオンシップの優勝/受賞を経てプロとしての活動をスタートを切るジャグラーも多いです。
◆International Jugglers’Association Juggling Festival Championships(国際ジャグリング協会ジャグリングフェスティバル チャンピオンシップ)
国際ジャグリング協会(International Jugglers’Association 略してIJA)が主催するジャグリングコンテスト。JJFのチャンピオンシップは、この大会を参考にしてつくられました。現在「ジャグリング世界チャンピオン」の看板を掲げて活動をしているパフォーマーのほとんどは、IJAフェスティバルでのコンテスト(チャンピオンシップだけでなく、道具別の競技会もあります。)の優勝者です。
日本のトップジャグラーのひとり矢部亮さんは、IJAでの優勝を経てシルク・ド・ソレイユの作品に出演するなど、世界を舞台に活躍しています。
国内でのジャグリングコンテストはJJFのチャンピオンシップが最大のものですが、近年それ以外のコンテストも増えてきています。
それらが今後どのような発展をして行くのか。
コンテストが多様になることで、日本のジャグリングシーンもいっそう深みのあるものとなりそうです。
ジャグリングから少し視野を広げて、サーカスコンテストにも目をむけると以下のようなものがあります。
◆Ciruque de demain(シルク・ドゥ・ドゥマン)
毎年パリで開催されるサーカスアーティストのコンテストです。
今年1月に開催された本大会では、国際的に活躍するジャグラー天平さんが、日本人としてはじめて出場し、特別賞を含む3つのショーを受賞。これは、歴代 最多受賞者になるそうです。
◆International Circus Festival(モンテカルロ国際サーカスフェスティバル)
モナコの王室によって1974年から行われている、世界最大規模のサーカスコンテスト。
「ジャグリングの神様」として現在も最高峰としてジャグリング界に君臨するアンソニー・ガットーが、2000 年にゴールデンクラウン賞をジャグラーで初めて獲得しました。
コンテストに加え、各種パフォーマンスフェスティバルへの参加をきっかけに、国境を越えて活躍をする日本人ジャグラーも近年増えて来ています。
己のジャグリングを磨く目標として、ジャグリングコンテスト。そして、そこで結果を出すことで、さらに広い世界へと飛び出す。そこに至るには鍛錬の積み重ねが必要なことは言うまでもありませんが、「プロジャグラー」としての王道は、確かに世界を舞台にして広がっています。
それが現在の日本のジャグリングのひとつの様相です。
コンテストを経て「プロジャグラー」になる。その先はどのような状況でしょうか。
歴史を振り返ると、芸能が発展するパタンのひとつとして、
路上→小規模な室内公演(移動可)→大規模な室内公演(移動可)→常設の劇場
という流れがあります。活動する社会の発展度合いによって「プロジャグラー」としての活動の「レベル」は様々に変わります。
シルク・ド・ソレイユは、そもそも大道芸人の集まりでありましたが、巧みな戦略が功を奏し、いまやマーケティングの見本になるようなビックビジネスになっています。
文化政策として政府の後押しを受けたフランスサーカスは、「ヌーボーシルク」として文化として豊かな芸術の土壌をつくり出しています。
また欧米では現在もパフォーマンスをする舞台のあるレストランやナイトクラブ、いわゆるキャバレーなどで日常的にジャグラーが活動する場所があります。
残念ながら海外のジャグリング事情と比較すると、日本の職業としてのジャグリングはまだまだ発展途上という感が否めません。長期の契約による劇場公演、というのは少なく、単発の公演を積み重ねて生計を立てるケースが大部分です。
ジャグラーの活躍の場にひとつであるサーカス。歴史のあるサーカスも日本にはありますが、年々減少しており、なかなか厳しい現実に直面しています。そんな中でもサーカスへの情熱を燃やし活動を続ける方々がいるので、サーカスシーンは今後大きな発展もありそうです。
もっとも先に述べたように、ショービジネスとしてのジャグリングは、すでにワールドワイドな展開をみせはじめています。活動の場を国内に限定する必要はないのかもしれません。すぐれた技術とそれをプレゼンテーションする作品があれば、世界がすぐ近くにあるのがジャグリングなのです。
最後に一点。
過去と現在が異なるのは「インターネット」の存在です。インターネットが発達した現在は、ウェブ中継などの、今までとは違った芸能の発展の仕方があるでしょう。今後は大規模な劇場での公演でなくても、たくさんの方に公演をみていただける場も増えて行くように思います。
ところで、今回は芸能という視点からジャグリングを眺めてきましたが、ジャグリングを仕事にするのに道はひとつでしょうか。
次回から数回に渡り「プロジャグラー」=「ジャグリングをもとに生計を立てる」道を考察して行きます。
おたのしみに。
ハードパンチャーしんのすけ
プロジャグラー。日本のデビルスティックのパイオニアとして、エンターテイナー、インストラクター、プロデューサーとして、日本全国で活動中。
- 【受賞歴】
アクア大道芸フェスティバルふれあい賞(2002)
日テレArtDaidogeiグランプリ優秀アーティスト賞(2004) - 【活動】
ジャグリング講師---関東にて6教室展開中。
ジャグリングイベントプロデューサー---現在は月に一回のライブ公演「門仲ジャグリングナイト」主催。
被災地応援パフォーマンス団 代表---東日本大震災被災者に「パフォーマンスで笑顔を届けよう!」と
プロジェクトを立ち上げました。 http://playforjapan.info - 【出版等】
教則本「デビルスティック大全」
DVD「FantasticDevilstick」 - 【メディア出演・掲載】
フジテレビ「笑っていいとも!」(2005)日本テレビ「赤鼻のセンセイ」(2009)NHK「極める!」(2010)
読売テレビ「教育ルネサンス~東大解剖」(2007)サンデー毎日(2009)FRIDAY(2009)
DVD『LICENSE vol.TALK SHINAGAWA』特典映像出演(2011)
意見、感想はこちらに! @shinnosuke_hp ハッシュタグを付けて呟いてね!#jugglingcolumn